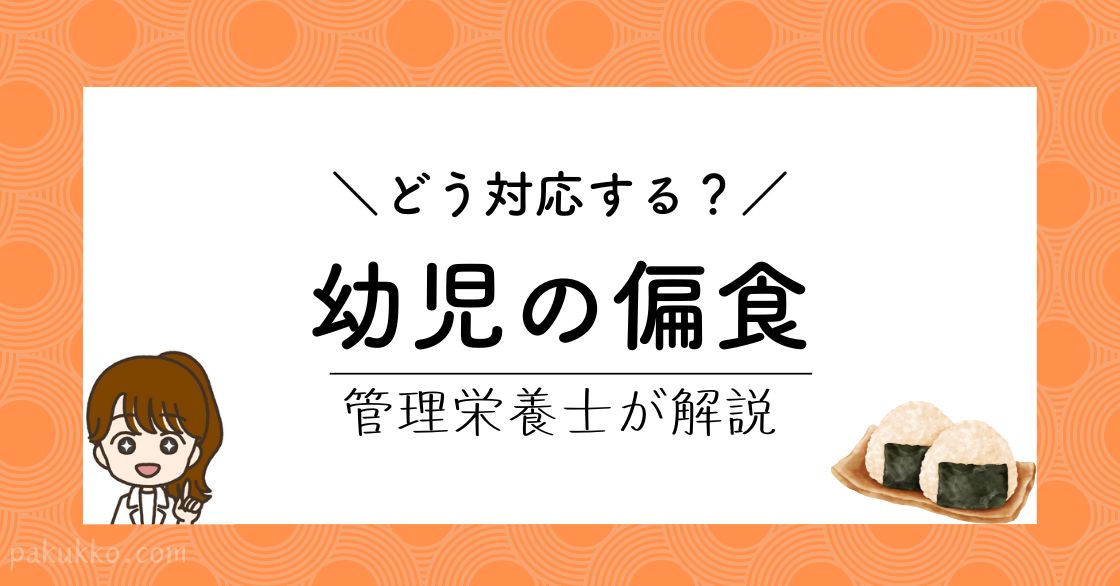子どもが偏食だと栄養バランスが悪く、心身の成長に悪影響が出てしまうのではないかと心配ですよね。
苦手な食材でも子どもが食べやすいよう工夫して調理したり、サプリメントを使用しているという方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、特定の食材しか食べないなどの極端な偏食は子どもの心身に影響が起こる場合があるため、対策が必要です。
「時間をかけて作ったのに食べてくれない」「野菜だけは絶対に食べない」など、子どもの偏食の対策や偏食になる理由などをこの記事では解説しているので、参考にしてみてください。
幼児の偏食とは?
偏食とは食べ物の選択が極端にかたより、体や心の成長に必要な栄養素がバランス良くとれない状態です。
好き嫌いのように『特定の食材が食べられない』ことは誰にでもあり、代替えできる食材を食べれば特に問題はありません。
しかし、偏食は「野菜全般が食べられない」「白米しか食べない」のように代替食品でカバーできない状態です。
偏食により食べられない食材の範囲が広すぎると、成長に必要な栄養素が不足し身体に悪影響を及ぼすため、改善する必要があります。
子どもの偏食はいつから始まる?
子どもの偏食は早くて離乳食後期(9〜10ヶ月)あたりから始まります。
最も多いのは自我が芽生える2歳~4歳で、大人になっても特定の食べ物が苦手で食べられない人がいるように、終了時期には個人差があります。
偏食をできるだけさせないためには、自我が芽生え始める2歳までに『うまみ』『塩味』『酸味』『甘味』『苦味』を経験させ、素材そのものの味を覚えさせるなど、食体験を積むと良いでしょう。
幼児期に偏食がある子供への対策9つ
子どもに偏食がある場合の対処方法は以下の9つです。
1つずつ解説していきます。
野菜を細かく刻んで料理に混ぜる
野菜を細かく刻んで料理に混ぜる方法は、偏食のある子どもに効果的です。
細かく刻み野菜の存在感を減らすことで、苦手意識を持たせずに栄養をとらせることができるでしょう。
スープやハンバーグ、餃子など味付けのしっかりした料理に野菜を細かく刻んで入れると、子どもが気づかずに食べられることが多いです。
少しずつ慣れることで、やがて野菜そのものにも抵抗が減ることが期待できるのではないでしょうか。
調理例
- ハンバーグ
- 餃子
- お好み焼き
- 肉団子の甘酢あん
- ミートソース
スイーツなどに加工する
スイーツのように、子どもの好みに合わせた甘い味付けに加工することで、野菜や果物を食べやすくなります。
例えば、野菜を使ったケーキやプリンのような見た目や味が工夫されたスイーツは、食べること自体も楽しい体験となり、苦手意識を克服しやすいでしょう。
何度か食べているうちに、そのままの形でも食べられる可能性が高まり、長期的な食習慣の改善に繋がります。
また、調理の段階で一緒に作ることで、子供自身が食材に親しみを感じるようになる効果も期待できます。
調理例
- パンケーキ
- 蒸しパン
- ポタージュスープ
一緒に野菜や果物を栽培する
一緒に野菜や果物を栽培することで、食材に興味と親近感がわきやすくなります。
「何を作りたい?」「どんな味だろう?」などの声かけをしながら収穫し、食べる楽しみや期待感を持たせてあげましょう。
子どもは知的好奇心を満たしたい気持ちから、苦手な食材でも口にしてくれる可能性が高くなります。

夏野菜は育てやすくそのままかじりつけるため、食育しやすいです。
一口でも食べられたら褒める
子どもが苦手なものを一口でも食べられたら褒めてあげることで、食事に対する自信を育むきっかけになります。
偏食のある子どもにとって、新しい食材を口にするのは大きな挑戦。
苦手なものでも食べようとする努力を認めて、「がんばってるね」と具体的に褒めることで、ポジティブな経験として記憶されるでしょう。
無理強いをせず、小さな成功体験を積み重ねることで、徐々に苦手な食材への抵抗感が薄れていきます。
声かけ例
「ブロッコリー、食べられたね!」
「トマトも△△(子どもの名前)ちゃんに食べられて嬉しいって言っているよ!」
絵本を一緒に読む
食材や料理がテーマの絵本を読むことで、子どもは食べ物に対する興味を楽しく持つことができます。
親子で絵本の内容を話し合ったり、絵本に登場する料理を実際に作る体験を通じて、子どもが食べることをポジティブに捉えるようになることが期待できるでしょう。
また、食材が成長する過程や料理が完成する楽しさを知ることで、食事への好奇心が育ち、偏食の改善にも繋がります。
無理強いしない
「無理強いしない」ことは、偏食のある子どもにとって、食べることを楽しい体験にするための基本です。
食べ物を無理に食べさせようとすると、子どもはプレッシャーを感じ、食事そのものに抵抗感やストレスを抱くようになる可能性があります。
むしろ、食材に興味を持たせる工夫をすることが大切。
料理を一緒に作ったり、少量ずつ試させたりすることで、自然と食べる意欲が育まれます。
子どものペースを尊重し、小さな挑戦を認めて褒めることで、食事に対する安心感と自信を育てましょう。



例えば牛乳が苦手なら、チーズやヨーグルトなどに置き換えてもOK。
遊び食べしても強く叱らない
子どもが食事中に遊び食べをしてしまっても、強く叱らないようにしましょう。
幼児期の子どもは、食べ物の食感や形状に興味を持ち、好奇心から遊び食べをしてしまうことがあります。
親として躾のために強く叱りがちですが、叱りすぎると、子どもにとって食事が「楽しい時間」ではなく「叱られる時間」になってしまいます。
その結果、食べる意欲を失い、偏食へ繋がってしまうことも。
遊び食べは発達の一環と考え、優しく注意したり、少しずつルールを教えながら見守る姿勢が大切です。
食事に集中できる環境をつくる
「食事に集中できる環境をつくる」ことは、偏食の改善に役立つ重要なポイントです。
テレビの音やYouTubeなどは食事に集中できなくなるため消し、食事中は家族全員が一緒に食卓を囲むようにしましょう。
また、食前にはおもちゃを片付ける習慣もつけておき、食事に集中できる環境を整えておきます。
静かで落ち着いた雰囲気を心がけることで、子どもが食事そのものに意識を向けやすくなります。
おやつを食前に与えすぎない
「おやつを食前に与えすぎない」ことは、子どもが食事で十分に栄養をとるために重要なポイントです。
食事前におやつを与えすぎると、子どもは満腹感を覚え、食事に集中できなくなりがちです。
特に甘いお菓子やスナックは、血糖値を急激に上げるため、一時的に満足感を与えるものの、栄養のバランスを崩す原因にもなります。
おやつは量を決め、食事の2時間前までに食べ終えておくことで、食事への意欲を維持することができます。
親が何でもおいしそうに食べる
親が何でもおいしそうに食べる姿を見せることは、幼児期の偏食対策として非常に効果的です。
子どもは親の行動を真似しやすい傾向があるため、野菜などの食材でもおいしそうに食べている姿を見せることで、子どもは苦手な食材に興味を持つようになります。
無理に食べさせようとするのではなく、食卓を楽しい雰囲気に保ち、家族全員でバランスよく食べる習慣を作ることが重要です。
子どもが偏食になる原因4つ
子どもが偏食になってしまう原因は様々ですが、主な原因は以下の4つです。



では、順に解説します。
食べ物の形状が好みではない
子どもは以下のような食べものを嫌がる傾向があります。
- 固いもの
- パサパサするもの
- 繊維の多いもの
- 口の中で散らばるもの
固い食材は柔らかく煮たり、パサパサしやすい食材はあんかけにしてとろみをつけるなどの工夫をすることで子どもも食べやすくなります。
体が味に対して防衛反応を起こしている
子どもは大人よりも味覚が敏感なため、苦味や酸味、渋みがある食べ物をイヤがります。
なぜなら、動物の本能として『苦味=毒を含んでいる食べ物』、『酸味=腐敗した食べ物』と認識するため。
苦みや渋み、酸味が強い食べ物を食卓に出す場合は大人がおいしそうに食べる姿を見せたり、子どもが一口でも食べたらしっかりと褒めてあげると効果的。
また、どうしても食べられない場合は食事自体がイヤになってしまわないよう、無理に食べさせず気長に待ちましょう。
食べ慣れないものへの警戒心が発動している
子どもは普段食べ慣れていない食べ物に警戒し、偏食することがあります。
警戒している食べ物は1度で食べさせようとせず、何度も食卓に出すことが大事。
大人がおいしそうに食べる姿を見せることも大事で、大人の姿を見ているうちに自然に拒否しなくなっていきます。
自立心の芽生えなど心の発達が起きている
2歳を過ぎ自我が芽生え、自己主張が強くなってくると、子どもの偏食が目立ち始めます。
2〜3歳ころに激しくなるイヤイヤ期が原因で偏食が起きている場合、無理して食べさせるのはご法度。
無理に苦手な食べ物を食べさせると、食事自体が嫌な思い出になってしまう場合があるうえ、ママやパパにも精神的負担が強くかかります。
年齢が上がると自然に食べ始める食材も出てくるので、他の食材で代替するなどしましょう。
子どもの偏食の特徴
子どもの場合「偏食」と「好き嫌い」の区別は難しいですが、偏食には以下のような特徴があります。
- えづく
- 吐き出す
- 噛まない
- 飲み込まない
- 新しい食べ物を拒否する
一方、好き嫌いは何度か口にしたり、成長に伴い子どもの味覚に変化が起こることで、味や食感などに慣れて食べられるようになることが多くあります。
とはいえ、子どもが好むものや食べやすいものばかり与えていると、栄養が偏ったり偏食に拍車がかかり、将来的に生活習慣病になりやすい食習慣が定着してしまうので注意が必要です。
偏食は子どもの発達に影響する?
偏食になると子どもの成長期に必要な栄養素を十分にとれません。
その結果、以下のような問題が起こります。
| 起こりうる問題 | 解説 | |
|---|---|---|
| 肉体面 | 発育不全 | タンパク質などが不足すると細胞やホルモンなどが正常に作られず、発育に影響が出てきます。 |
| 免疫力の低下 | バランスのよい食事をとり、まんべんなく栄養素を摂取することで、免疫力を高められます。 | |
| 便秘 | 腸内環境を整えるためには、食物繊維だけでなくさまざまな栄養素が関係しています。 極端な偏食をしてしまうと、腸内環境を悪化させ便秘が起こりやすくなります。 | |
| 生活習慣病や肥満 | 生活習慣病は成人してからと思っている人も多くいますが、スナック菓子やジュースなど栄養バランスの崩れで子どもでも発症する可能性があります。 | |
| 精神面 | 癇癪 (かんしゃく) | ビタミンやミネラルなどが不足すると精神面に症状が現れやすくなります。 不安感、協調性の低下、集中力の低下、怒りやすくなるなど精神面の悪影響が起こることがあります。 |
偏食のために栄養のバランスが大きく崩れると、上記のような問題が出てきます。
「子どもの好き嫌いなので仕方ない」「そのうち治る」と放置せず、少しずつ食べられるよう努力していく必要があります。
子どもの偏食でよくある疑問
子どもの偏食でよくある疑問をまとめました。
ご飯を食べない分、お菓子をあげていい?
お菓子には体に必要な栄養素がほとんど含まれていないため、食事として出すのは避けましょう。
食材に置き換えられるおやつ、例えばおにぎり・バナナ・ヨーグルト・パン・焼き芋・チーズなどが良いでしょう。
苦手なものを食べるには?
苦手だから食べない、と決めつけず食べない理由を考えることが大切です。
噛み切れないから、口に繊維が残るから…など子どもが食べない理由は様々。
また、子どもが好まないメニューでも大人が食べるのであれば、食卓に出し続けてみましょう。
年齢が上がるとともに口にする可能性もあります。
偏食・好き嫌いで発達に影響がある?
記事冒頭で解説したように、心身に影響が出る可能性があります。
ご飯の量が足りているかの目安は?
子どもに必要な栄養をまとめた記事があるので参考にしてみてください。
味の濃いものが好きだけど大丈夫?
1日のトータルで塩分量を考えるとよいでしょう。
1品しっかりとした味付けのものを用意し、他は薄味にするなどの工夫ができます。
『うま味』『酸味』などバランスよく使うと薄味でもおいしく感じられます。
また、カリウムはナトリウム(塩)を体外に出す作用があります。
カリウムの多いバナナや海藻類などをメニューに入れるのも一つの手です。
子どもの偏食(好き嫌い)はどう対応する?まとめ
子どもの偏食は早いと離乳食後期あたりから始まり、個人差がありますが大人まで続く場合があります。
野菜全般が食べられないなどの激しい偏食は、とれる栄養素が極端に偏るため、成長期の子どもにとって悪影響を及ぼします。
食べないと親は心配のあまり、食べることを強制したりしがちですが、その子自身に合った克服方法をえらび、食べることを無理強いしないようにしましょう。